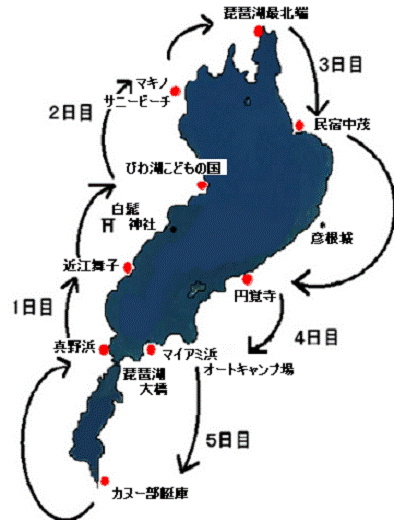2011年1月2日 熊本名誉会長宅にて(左が現主将の竹部君)
2011年1月2日 熊本名誉会長宅にて(左が現主将の竹部君)
 奥様もお元気(左が現主務の黒河君)1988年卒 水嶋君提供
奥様もお元気(左が現主務の黒河君)1988年卒 水嶋君提供
OB・OG寄稿文
―京大カヌー部卒業!―
熊本 水賴(OB会名誉会長)
平成20年10月25日、関学カヌー部創部50周年記念祝宴に招かれて出向いたところ、いきなり創部当初の面々、坂根徹君、河村恵吾君などなど、懐かしい顔ぶれから異口同音に「僕たちは京大カヌー部卒業です」という挨拶で温かく迎えられた。いっぺんに熱いものが込み上げてきた。
彼等がカヌーに興味を抱いて先ず教えを乞うたのは高木公三郎先生だが、昭和35年、36年と発足当初の日本選手権を制覇した関学チームの練習拠点は瀬田川であり、艇庫は京大カヌー部艇庫であった。その艇庫は京大ボート部が艇庫を移築する際に1スパン無くした(故意か偶然か?)ためエイトが入らなくなったので、高木先生がカヌー部のために貰い下げてきた代物であった。京大ボート部のOB重鎮でもあった高木先生の深謀遠慮か。「熊さん心配ないよ、その内誰も何も言わなくなるから・・・」
当時、関西にはカヌー艇庫は京大のものが唯一で、関学をはじめ武庫女、立命、大商大,等々みんな収容して上げていた。学生部の職員が監査に来て、「内の艇より他校の艇の方が多い。引き上げさせて欲しい」と言うので「京大1校ではレガッタにならぬ.他大学のカヌーも育ってくれてはじめてレガッタが成り立つ」と苦言を封じた一幕もあった。
しかし、そのため後藤君はじめ創部当初の部員諸君には大きな負担も背負わせてしまった。昭和38年11月、関西ではじめてカヌー選手権大会を開くことになったが、ボートと同じくJR在来線鉄橋をスタートとし、京大ボート部艇庫をゴールとする曲がりくねった瀬田川コースである。明日にレースを控えた現役選手が後藤君を筆頭にコンクリートを捏ね、半切りの石油缶に流し込んで手製のアンカーを作り、手こぎボートを操りながら、土木測量実習の成果を活かして要所要所に標識ブイを浮かべて難しいコースを完成させた。徹夜の取り組みは見事であった。
「僕たちは京大カヌー部卒業です」これはカヌー競技草創時代、献身的に下支えした京大カヌー創部期の部員諸君の苦労を知る仲間からの、心からの謝辞である。
偶然 それとも
菅澤 正秀(1969年卒)
最近体験したちょっと不思議な出来事を紹介させていただきます。
2・3年前、岡崎の京都市美術館へ絵を見に行ったときのことです。 阪急電車が京都に近づいてきたとき、ふと「今日は時間に余裕があるので、美術館に行く前に仏光寺にある塔頭に寄って行こう」と思い立ちました。大学時代以来親しくしていただいた故高木公三郎先生(京都大学名誉教授。関西学生カヌー連盟初代会長)ご夫妻のご葬儀が行われたお寺です。
実はかねてより一度先生のお墓参りをしたいと思いながらも、お墓の場所がわからないため果たせずにおりました。その塔頭はおそらくご夫妻にご縁のあるお寺で、お墓のことも教えていただけるのではと考えたのです。
河原町駅から10分あまり歩いてお寺に着いた時です。何と先生のご遺族の方々がお寺から出て行かれるところに出くわしたのです。皆さん喪服姿です。突然現れた私を見て「え、どうしてここに?」と驚いておられます。私も一体何が起こったのか事態がのみ込めませんでした。
お話を伺うと、奇しくもたった今、先生の17回忌の法要を終えたところだというではありませんか。なんというタイミング。偶然というにはあまりにもできすぎです。
電車内で仏光寺に寄って行こうと思いついたときは、恐らく法要の最中だったのではないでしょうか。一本早い特急に乗っておれば、ご焼香もさせていただけたかもしれません。
学生時代からずっと可愛がって下さった先生が、私のことも忘れずに呼んでくださったのかと、胸に熱いものがこみ上げてきました。 やはり霊魂は存在するということなのでしょうか。
「意中、人あり」という言葉があります。意識の中に私淑する人を常に持っているという意味ですが、改めてその幸せを感じたのでした。
以来時々お墓にお参りし近況報告などしています。
昨年も似たようなことがありました。
国立京都博物館で「妙心寺の名宝展」が開かれたとき、学生時代に作品を見て気に入っていた桃山時代の画家、海(かい)北友松(ほうゆうしょう)の代表作が出品されることを知り出かけました。
久しぶりに見た友松の、武家の出らしくスケールが大きい凛とした作風に、改めて大きな魅力を感じました。同時出品の長谷川等伯や狩野派の作品も素晴らしく、実に見ごたえのある展覧会でした。
会場を出た後、学生時代カヌー部のトレーニングでよく駆けていた吉田山、さらにその奥の真如堂といった大学周辺の思い出の地を、三・四十年ぶりに懐かしく巡り帰ってきました。
宗忠神社の石畳の傾斜を二人一組の手押し車で登ったことや、吉田山をこえ真如堂の本堂の柱にタッチして往復したランニングのことを思い出しました。あのころは元気でした。
その後しばらくして、友松のことをもう少し知りたいとインターネットで検索してみたところ、なんと彼の墓が当日立ち寄った真如堂の墓地にあるというではありませんか。
そこで後日あらためて真如堂を訪ね、墓を探し当て手を合わせてきたのですが、前に訪れた際、何も知らないままその墓のごく近くにある鐘楼に立ち寄っていたのです。何十年ぶりかに見た絵の作者の墓が、同じ日何十年ぶりかに訪ねた寺にあったのです。
これも単なる偶然とは思えず、今回もひょっとして友松が呼んでくれたのではないかと勝手に想像しています。
ちなみに友松の墓の隣には、親友の斉藤利(とし)三(みつ)の墓があります。
斉藤利三は明智光秀の重臣で、山崎の合戦の後捕らえられ処刑された後粟田口でさらしものにされていたのを、友松が番人を蹴散らし遺体を奪い返し、真如堂に埋葬したと言われています。そして友松の死後は、本人の遺言により斉藤利三の隣に埋葬されました。
仲良く並んだ二つの墓は目立たないものの、信義を貫いた証として、これからも見る人の心をとらえ暖かいものを呼び覚ますでしょう。 現役時代のランニングといえば、冬の間はよく狸谷不動尊まで往復しました。そのコース脇に金福寺というお寺があります。今年その裏の岡に、最近興味を持っている与謝蕪村と呉春ほか高弟たちの墓を発見しました。
京都というのは何とも奥が深いところだと今ごろ気づかされています。
いずれもお墓に関する話で恐縮ですが、こういう体験をするというは、ひょっとしたら毎朝仏壇に手を合わせ、毎月墓参りを続けている間に、あの世との距離が少々縮まってきているのかも知れません。
といっても身体のほうは、最近の健康診断でも特に異常なしということで、時間距離で言えば、あの世はまだまだ遠い先だと思っていますが‥‥。 そのうち別の故人とも縁が結ばれるようなことがあればと、少々妙な期待もしています。
さらにもうひとつ。
些細なことですが、今乗っている車のナンバーが、「す・××××」
菅澤の「す」に、我が家で母が使っている電話の番号と同じ××××。何の注文もしていないのに、取得したのは我が家に縁のある番号でした。このような番号に当たる確率は果たして何分の一になるのか考えてみると、これも偶然すぎる出来事です。
最近たまたま読んだ、歴史小説作家、吉村昭の随筆にも、普通ではあり えない信じ難い自身の体験を2・3紹介した上で、「途方もない偶然と偶然を結びつける何かがこの世には存在するらしい」と結んでいました。同じような不思議な体験をしている人が他にもいるのです。
偶然なのか、あるいは何か見えない力が働いているのか。理屈では説明できないことがこの世に存在する。人智の及ばないことがあるということで何か嬉しくなってきます。
人間なんてちっぽけな存在なのだと、改めて感じているこのごろです。
高木公三郎先生について
高木 公三郎 (たかぎ きみさぶろう)先生について若手のOB・OGは良く存じ上げていないと思いますので、ご紹介を挿入しておきます。
高木先生は明治40(1907)年生まれ。昭和11(1936)年に京都帝国大学理学部を卒業されています。大学ではボート部のコックスとして活躍されましたが、ベルリンオリンピック(1936)には、当時ドイツに留学中だった先生はボート選手団の役員として参加されています。その際、次の東京オリンピック(結果的には日中戦争のため日本が返上)でカヌー競技(ベルリンオリンピックから正式競技となっていた)を開催する必要があることから、高木先生はカヤック、カナディアンカヌー、パントなどの小艇数艇を購入して日本に持ち帰り、琵琶湖の桑野造船や東京のデルタ造船にコピーを作らせながら、漕法の指導をはじめられました。これが日本の競技カヌーの始まりです。戦後はファルトボートを作るなどして地道に普及に努められ、日本カヌー協会が再建される1年前の1959年に関西カヌー協会を発足させて1964年の東京オリンピックで日本がカヌー競技を開催する準備をされました。
先生の理学部でのご専門は天文学で、前大戦末期には南京天文台長を務めておられました。戦後の学制改革に当たり、時の京都大学鳥養総長に呼び出され、新設される保健体育の運営を任されました。そして、新学科の運営に当たりながら、身体運動学の研究分野を切り開いてこられました。 先生のお考えを表す言葉として、著書「身体運動の基礎」の序文の一節をご紹介しておきます。
『身体運動学は、理論と実技の結びつきである。体育運動やスポーツの指導は、合理的な身体活動を通じてはじめて本当の成果をあげ得るものであり、それに当たる人々は身体運動学的な知識を明確にもっていなければならない。』 http://www.gakugei-pub.jp/mokuroku/book/ISBN4-7615-0015-8.htm また、先生は絵画にも秀でた才をお持ちで、主著にあげられる『身体運動学』『身体運動の科学』(共に学芸出版社)の中の骨格や筋肉の描画は高く評価されています。
高木先生のお人柄を偲ばせる逸話を2つ。
高木先生は学生時代に赤子をおんぶして登校されていた、と後藤は誰かから教えてもらったことが有ります。その赤子だった方が後に名古屋大学の教授になられた高木不折先生で、カヌー部の創設期には後藤が在学していた京大工学部土木工学科の教員をされておられました。
もう一つは、1964年東京オリンピックの1年ほど前に起きた当時の日本カヌー協会のタイム短縮発表事件への対応です。もう公言してもよいと思いますが、相模湖で行われた第5次オリンピック選考会で、一部の協会役員がレースタイムを10秒ほど短縮して発表しオリンピックで入賞可能なように装ったのです。これを契機に関西の役員と関東を中心とする役員の間で確執が起りました。このままではカヌー競技界のモラルが問われる、せめて学生だけでもマットな道を歩いてほしい、それには京大カヌー部が先導的な役割を果たして欲しい、と当時の主務だった野崎に高木先生から、更には熊本先生からもお話がありました。
もともとカヌー協会のオリンピック選考予選のスケジュールが学生の試験のタイミングなどを考えず自衛隊乃至は社会人の都合だけで作られていたというようなこともあったので、ここは学生の立場も主張できる組織を作らなければということになり、野崎が奔走して東京の慶応・大正・専修などの大学と相談の上、関西が先に作るほうが抵抗が少ないということで関西学生連盟を作ったのです。この動きは高木先生と熊本先生に相談づくでした。そして、関西から関東および全日本学生連盟が作られていきました。
なお、日本カヌー協会は1980年に社団法人日本カヌー連盟に組織変更、2010年には公益社団法人日本カヌー連盟に移行しています。現在の日本カヌー連盟には京大カヌー部のOB諸氏が役員に就任され、活躍されています。
副会長:山本和彦、常務理事:本田 彰、常務理事:上田忠雄、理事:有山行基。連盟の会長は元首相の福田康夫、理事の総数は23名です。
(文責:後藤、野崎(暁)、前ページのご紹介文は熊本先生に協力いただきました。)
2010年のカヌー雑感―日本は世界に対抗できるか
山本 桂嗣(1969年卒)
はじめに
今年3月63歳退職後地元「湘南カヌークラブ」小此木雪江氏のすすめで「神奈川県藤沢市カヌー協会」と上記クラブに入会した。9月に第3回かながわカヌー運動会、11月に藤沢市市民総合体育大会カヌースプリント競技、12月に八景島カヌーツアー(有志)に参加した。木製の左固定デルタ製パドル:S41年度関西カヌー選手権JK-2/500m第1位の相棒黒川直樹氏より借用中、のパドルを使ってスラローム艇、シーカヤック艇を楽しんだ。昨年6月の隅田川下りツアー:14km、ペア山崎さん、に続いてカヌーが急速に身近になってきた。
今年のアジア大会で優勝者
今年のアジア大会K1-200mで松下桃太郎氏と北本忍氏がともに優勝したことは画期的であった。桃太郎氏は知る人ぞ知る少年時代からそのパフォーマンスで話題を呼んでいた。日本もカヌーで金メダルがとれるのだ!と実感した。
今までなぜ弱かったのか
今の日本の青少年のスポーツ事情をみると、先ずサッカー、野球と来る。体力などスポーツに恵まれた子供がマイナーなカヌーに入ってくるか?という現実がある。わがクラブでも野球をしながら合間にカヌーに乗る子供もいるという。もしスポーツ能力に恵まれた子供を全国レベルで選抜し練習すれば日本もずっと強くなるのではないか。
スポーツの環境、条件もハンディ?
例えば中高学生が全国の大会に出る場合当然ながら艇を運ぶのだが、費用が馬鹿にならない。練習場所も限られる。近場のもの以外なかなか練習できにくい。そのような環境、条件のハンディを乗り越えればカヌーは今回のアジア大会を契機に日本でもブームになるのではないか。隣国のゴルフブームのように。そのような初夢を見ようと思う昨今である。 (了)
近 況 報 告
奥野 和夫(1974年卒)
昭和49年卒業の奥野です。あまり皆様に紹介できるようなことがありませんが、めでたい「河奴」再発刊の賑わいにと当時のカヌー部のことに加えて、私の仕事のこと、家庭のことなどについて近況を報告させていただきます。
<当時のカヌー部のこと>
- ・実家が滋賀県草津市で、大津市膳所までの高校通学電車で瀬田川を渡っている時に見たアメンボウのような優雅なカヌーを見て入部
- ・入部後は、大きな先輩達の中で、体力の無い私でも何とかやり抜けた4年間、いくつかの大会で賞状を頂いたことも
- ・民家を借りての夏の合宿、食事当番、冷やし飴、力餅うどん屋のおねえさん
- ・カヌーでの琵琶湖周航
- ・高島屋配送センターでのお歳暮の包装作業、祇園祭での鉾夜警と巡行作業、葵祭行列などカヌー部活動費稼ぎ
<仕事のこと>
- ・農林水産省に勤めて30年間勤続、その間愛媛県松山市、名古屋市、大阪市等に単身赴任
- ・縁あって菓子製造メーカ等で組織する全日本菓子協会という団体に再就職して、お菓子の消費拡大キャンペーン、原料問題、表示問題、環境問題等に関しての行政に対する陳情活動など業界活動に従事、最近の役人の不甲斐なさに憤慨
<家庭のこと>
- ・Ⅱ型糖尿病と診断され、毎食前に食後の血糖値を下げる薬を服用中、運動をする必要に迫られていますが、優柔不断でなかなか長続きせず
- ・南箱根に富士山の見える温泉付き別荘を購入、妻と月のうち1~2週間のペースでリラックス
- ・長女は東京地検で全国最初の裁判員裁判を担当し、長女の夫は埼玉で全国2番目の裁判員裁判の主任弁護士を担当
- ・長男は某カメラ会社に勤め、目下婚活中
 2011年1月2日 別荘ではなく新幹線の車窓から(著者とは関係なし)
2011年1月2日 別荘ではなく新幹線の車窓から(著者とは関係なし)
私の京大カヌー部時代フォトブック
~『河奴』の復刊に寄せて~
大橋 弘幸(1975年卒)
皆さんご無沙汰しています。私が琵琶湖の瀬田浦にいたのはなんと40年も前のことになります。 旧『河奴』に「私の阿弥陀籤」と題して寄稿したのが10年前頃でした。京大カヌー部OB・OG会の関東地区新年会を学士会館で開催するようになってからでも5年は経過しています。
今回、後藤先輩の肝煎りの名簿不明者捜索に皆さんが協力している様子を知って、早速私も40年程前の記憶を辿ってみました。京大時代の写真アルバムを引っ張り出したところ、懐かしい写真を発見しましたので公開します。正にお宝写真です。
私が京都大学農学部に入学したのは1971年4月。早速クラブの入会勧誘の渦に捲き込まれました。何を思ったか、気がついたら全く縁のなかったカヌー部に入部し、吉田の体育館での筋トレと瀬田漕艇場でのカヤック漕ぎ訓練に明け暮れていました。当時は学園紛争がまだまだ頻発し、よくバリストが張られ京大キャンパスでの講義は休講続き。ここは体力養成と体を鍛えたのでした。その頃のことは前稿「私の阿弥陀籤」に書きました。日に日に腹筋が鍛えられ、まるで阿弥陀籤のようにと。
一枚目の写真は入部間もない、1971年6月27日の京都選手権大会JK-1に出場したときのもので、4位入賞との記録がありました。
 試合前の締まった(笑)表情の私。
試合前の締まった(笑)表情の私。
続いて恒例の祇園祭で京大カヌー部が『橋弁慶山』を曳いた時のもの。1971年7月17日のことでした。京都の町屋で山の組立から手伝い、山鉾巡航の曳き手を務めたのは実に思い出深いものでした。中央の私の後ろに、右から同期の早川、確か主将の西村さん、松田、八木、山崎の顔が見えます。
 次の写真の烏帽子を被ったのは同期の矢入だと記憶しています。
次の写真の烏帽子を被ったのは同期の矢入だと記憶しています。
 中央は現在も親交のある宮本さんです。
中央は現在も親交のある宮本さんです。
夏の1ヶ月に及んだ瀬田合宿の最後は、関西カヌー選手権大会でした。1971年8月5日から8日までの4日間。私は半場とペア組みJK-2に出場し、4位に入賞しました。私の人生、スポーツで公式な記録として得た賞状はこれだけです。半場のその後の消息は全く知りません。経済学部生で、黒ヘルも被っていたような記憶がかすかに。この時の優勝は山崎・早川ペアでした。さすがに、カヌー部を四年間全うしたのも同期ではこの二人だけでした。やはり表彰台と4位以下には大きな違いがあったわけです。
 この写真の撮影日は明確ではないのですが、合宿明け1971年夏の終わりの頃でしょう。
この写真の撮影日は明確ではないのですが、合宿明け1971年夏の終わりの頃でしょう。
私のカヌー部時代は、この後、秋の筋トレと左大文字の如意ヶ岳や金閣寺までのランニングに続き、お歳暮シーズンに河原町の大丸百貨店で包装のアルバイトでクラブの活動費稼ぎに行きました。それから冬場はなぜか応援団にも在籍し、学ランを着て京大アイスホッケー部の京大-東大選の応援に声を枯らしました。そのころ応援歌「新生の息吹」や京大学歌、「琵琶湖周航の歌」を覚え、今でも口をついて出てきます。
翌年1972年の夏は北海道1ヵ月周遊ユースホステルの旅、1973年夏はUC BerkeleyのSummer Extensionに1ヵ月間参加しました。そして1974年の夏は大学院受験勉強に費やしましたので、私のカヌー部時代は1971年で事実上幕を降ろしたというのが実録です。
その後大学院を経て味の素株式会社に就職。関東に上京してから、かれこれ34年が過ぎました。近況ですが、2010年4月から東レ株式会社に勤務しています。東レから要請を受けて東レに移り、ライフサイエンス領域の海外事業を担当しています。勤務地は鎌倉-日本橋-浦安-ロンドンと巡回しています。
60歳まであと2年となりましたが、心身とも至って元気でチョイ悪オヤジを実践中です。
今年は終に孫まで得て、おじいちゃんと呼ばれて戸惑っています。
カヌーからは縁遠くなりましたので京大カヌー部OB・OG会が唯一の接点です。しかし、いつかあの清流四万十川でカヌーを漕いでみたいと夢想しています。
(2010.12.29記)
ふるさと大分に帰って、早や32年
畔津 義彦(1977年卒)
東京にも関西にも遠い九州はふるさと大分に帰って、早や32年。県庁生活も残すところ3年ほどになりました。(定年が延びるという噂もありますが?)
振り返れば、帰郷してすぐに熊本先生のご協力のもとに仲間と立ち上げた県カヌー協会も、最初は運営に四苦八苦していましたが、島根県からの強力な助っ人、堀田育子嬢が高校生を育ててくれたおかげで、県体育協会の中でも重点強化種目となり、国体でも毎年のように多くの得点を稼ぐことが出来るようになりました。私自身はもうほとんどカヌー界には関わってはいませんが、大分川に多くのレーシングカヌーが浮かんでいる風景をみるたびに、琵琶湖の漕艇場や瀬田川での練習を思い出します。
私自身は県庁の土木技術職員として県下の土木事務所ではもっぱら道路整備事業に携わってきました。20代のときに関わった県下初の自動車専用道路(約20km)は補助事業や有料道路事業、さらに単独事業を組み合わせた、大分県独自方式のプロジェクトでしたが、先月、とうとう無料化されました。一方、本庁では都市計画畑が長く、平成6年から計画に携わった、JR日豊本線の連続立体交差事業を中心とした大分駅周辺の総合整備事業が現在、最後の山場を迎えています。鉄道が初めて通って以来戦災復興を除けば、100年ぶりに大分市の中心部が大きく変わっていく機会であり、多くの市民、県民が関心を寄せています。私としてもこのような場面に出逢えることは大きな幸運だと考えています。
しかしながら、最近の社会資本整備を取り巻く環境はとても厳しいと言わざるを得ません。これからどのような地域づくりを進めていくべきか、どんどん高齢化が進行している田舎を眺めながら、悩ましい課題が山積です。
何はともあれ、これからの人生を行動的に過ごすべく、体力づくりを兼ねて、自宅から県庁までの片道4kmほどを原則として徒歩通勤とし、休日には2時間ほどバドミントンを楽しんでいます。
なかなか東京での新年会や関西でのOB会に出席できませんが、大分には多くの温泉とうまい魚や焼酎がありますので、九州へお出での折にはぜひ声を掛けてください。
フィリピン・シキホール島より
井上 徹(1982年卒)
前回 私が河奴に書いた記事は、OBになってもカヌーの試合に出続けているという内容でした。今回も他の人とは変わっていて、10年余り住んでいるフィリピンでのプロジェクトについて紹介します。
私がフィリピンに来ることになったきっかけは、亡くなった父親が第二次世界大戦中、当地で戦っていて 子供の頃から その話を聞いていたことです。父は航空隊に志願し、特攻隊で出撃したものの、幸か不幸かエンジントラブルで 爆弾を抱いたまま不時着して、予定外に帰還しました。不時着したイロイロという場所がどんなところか私は、一度行ってみたくなりました。フィリピンは、日本人には危険なイメージがつきまといますが、来てみると、特に田舎の島では、治安が良く、人々はフレンドリーで居心地がよいので、そのまま居付いてしまいました。現在はセブ島の南にあるシキホール島の海岸沿いに小さな家を建てて住んでいます。
現地では、以前から興味があったことで、貧しい人たちの支援のプロジェクトを続けています。と言っても 人のやらないことをやりたがる私の性分で、「ボランティア20の実験」と称して、新しい取り組みを試行錯誤で進めています。実際には、いろいろと難しいことが多いので、最初から3勝17敗を目指し、何か3つ、他の人にもお奨めできる取り組みのネタを紹介できたら良いなと思っています。一方では、失敗が目的とも言えて、うまくいかなかった話も、インターネットで詳細に公開しています。それを踏み台にして、次のステップへと進んでくれる人が現れることを期待してのことです。私一人で支援活動を始めても、大海の魚に餌をばら撒いているようなもので、いくらやっても足りません。しかし、試した結果を公開して他の人の参考にしてもらえれば、いくらでも広がる可能性があります。
インターネットによる情報公開が手段であり、目的でもあります。
以下、プロジェクトの例をいくつか紹介しておきます。
ラーニングセンター・プロジェクト
3年前から、小浜市のNPO ティームスの方と共同で、ラーニングセンターを始め、溶接やパソコン、ミシンなどの職業訓練を行っています。最近ではプレハブのモバイル教室も作って、神出鬼没に、山奥などでも、授業が行える体勢を整えようとしています。
と言っても課題は、日本も同様になりつつありますが、仕事がないことです。最近は現地でもインターネットがつながるようになり、パソコン・インターネット上だけでできる仕事が見つかれば良いなと特に願っております。誰か、現地の人々に仕事を提供して頂ける方はいませんか?
 Photo_1 ラーニングセンターでの溶接実習の様子
Photo_1 ラーニングセンターでの溶接実習の様子
カウ・ガールズ・プロジェクト
フィリピンは海外出稼ぎ立国で、900万とも1000万とも言われる海外出稼ぎ組みが居ます。このプロジェクトでは、貧しいが勤勉な学生と家族に牛を育ててもらい、それで学費を稼ぎ出し、大学の看護コースを卒業し、ナースとして外国に出稼ぎに行くというものです。特に米国へ行ければ、収入は現地に比べ 二桁近く増えるので、今度は、次の世代の貧しい学生を沢山支援してもらい、Pay forwardで指数関数的に支援の和を広げようという壮大な計画です。
 Photo_2 カウ・ガールズ・プロジェクトで牛の世話をする女の子
Photo_2 カウ・ガールズ・プロジェクトで牛の世話をする女の子
子供たちへのノートパソコンの貸し出し
日本のオークションで落札した数千円のノートパソコンを現地の僻地に住む貧しい家の子供たちに貸し出して、何か良い結果が出ないか試しています。
 Photo_3 貸し出したパソコンを使う子供たち
Photo_3 貸し出したパソコンを使う子供たち
実際には、どのプロジェクトも問題が多くて、日々悪戦苦闘しています。例えば、肥育のため人工授精で良血の牛を生ませようとしたら、この牛だけは、子供を作らないで欲しいと思うチビのオス牛の子供ができたことがありました。生まれた子供も小さくて、親同様、目の周りに狸のような輪があるので、一目で分かりました。
最後に一言。カヌー部OB,OGの皆様には、社会の第一線で活躍されている方がほとんどで、私のような、はみ出した人生を送っているものは稀だと思われます。ただ、何かの都合で、駆け込み寺が必要な方もおられるかもしれず、それに近いような場を提供できれば良いなとも思っています。現地では、自宅以外にコテージをいくつか建てて、無料で泊まれるようにしてあるので、いろいろな人がやってきます。気が向けばお立ち寄り下さい。
以下のURLでいろいろ情報を提供しています。
http://www.millionmiler.com/philippines/index.html
アラスカの四季
浅井 正秀(1984年卒)
学生時代あれほど没頭し、思いで深い数々の戦績もあげさせて頂いたカヌーですが、卒業と同時に全く縁がなくなってしまいました。卒業後レーシングカヌーと接したのは10年以上も前の福岡国体で審判を務めてお手伝いをした程度でしょうか。従って、カヌーに関連した投稿をしたくても話題がございませんので、それはあきらめて、仕事にまつわる四方山話でも書かせて頂きます。
卒業後水産会社に就職し、度重なる転勤の末、5年前にシアトルにまで来てしまいました。思い起こせばこの5年間、四季おりおりの魚を求めてアラスカ各地を徘徊しました。今回は皆さんの食卓に多少なりとも縁のあるアラスカの話を種に近況報告させて頂きます。
冬 : 明太子 (めんたいこ:スケソウダラの子)は金の卵
皆さんがスーパーで買うタラコ、あるいは、博多に出張したらお土産で買う辛子明太子のかなりのものがアラスカから来ています。アメリカはカニや鮭など多様な水産物を日本に輸出していますが、額的に最も大きいのは実は明太子(スケソウダラの子)です。スケソウダラは世界最大の単一水産資源の一つで、アメリカ経済に多大な貢献をしています。アラスカのベーリング海がその漁場で、毎年1月20日にスケソウダラ漁は始まります。筆者は毎年この季節になると我社の工場があるダッチハーバーに赴き、必要あれば漁船に乗り込んだりします。ダッチハーバーはパールハーバーと同様第二次世界大戦時に日本軍が空襲したアメリカ領のひとつで、現在は人口4,000人くらいのアリューシャン列島にある小さな村ですが、全米で最大の水産資源水揚港でもあります。冬の季節にダッチハーバーに行くのは容易ではありません。シアトルからアンカレッジまではスムーズにいきますが、アンカレッジからダッチハーバーまでの便は天候の理由でいとも簡単に欠航します。筆者もアンカレッジで5日間も足止めされたことがあります。従って、ダッチハーバーからの帰路も同様で、ダッチハーバーで大怪我をすると大変な事態になります。天候が悪化し数便が欠航すると空港は空席待ちの長蛇の列となり、いつアンカレッジに戻れるかわかりません。命に関わる怪我や病気なら緊急対応されますが、水産業の現場につきものの多少の負傷は考慮されません。先日、筆者も長蛇の列に並んでいましたら、痛みで顔を引きつらせた男が前に並んでいたのでどうしたのかと尋ねると、漁船上で指を切断したとの事。包帯でぐるぐる巻きにして一応指を接続させているようでしたが、早くアンカレッジの病院いいかないとくっつく指も付かないじゃないかと苛立っておりました。
ベーリング海で漁獲されたスケソウダラは、ダッチハーバーにある数ヶ所の陸上工場で加工されるか、加工設備を備えた加工漁船上にて加工されます。卵はすぐに冷凍され、魚の身の部分はスリミあるいはフィレーにされます。タラコなんぞを食べるのは日本人と韓国人くらいなもので、実際はそのほとんどが日本に輸出されます。
スケソウダラの抱卵期は1月から3月で、各社が生産した2万トンにものぼる明太子は3月・4月にシアトルで行われる入札会で一斉に販売されます。入札シーズンのシアトルは日本の辛子明太子会社や水産会社のバイヤーがうろつき異様な雰囲気となります。落札者は船積書類引き換え即金払いをしなくてはならず、4月の米国水産会社の銀行口座には総額で200億円以上のキャッシュが入金されるというわけで、明太子は今やアメリカにとって金の卵なのです。
春 : 今、世界の流行の最先端をいく食べ物はカニかま
海外に住んでいると日本のテレビ番組を楽しむ機会が激減します。今、日本では「トレビアの泉」という番組がヒットしているという事で、先日友人から借りたビデオで初めて見ました。家族で「へー!」を連発して爆笑しながら見ていたところ、非常にうれしい内容の項目がありました。「今、世界の流行の最先端をいく食べ物はカニかま」との事なのです。カニかまがフランスで爆発的に売れているという内容の話題なのですが、この原料も実はアラスカから来ているのです。明太子が取り出された後の魚の身の部分はスリミかフィレーに加工されます。フィレーはマクドナルドのフィッシュバーガー等になりますが、スリミは世界中に輸出され練製品に加工されます。日本では練製品といえば蒲鉾・竹輪など色んな物がありますが、欧米には練製品といえばカニかまくらいしかありません。逆に練製品を世界的な食品にしたのがカニかまで、フランスではここ数年、カニかまの消費が年率20%の勢いで伸びています。筆者は冬の間ダッチハーバーでスケソウダラにまみれ、シアトルで明太子を販売した後は、今度はスリミの販売で世界中を旅する行商人と化しますが、フランスは最近最も力を入れているマーケットです。世界の流行の最先端の食べ物の原料を販売しているのかと納得しながら、この番組の着眼点はすばらしいと思った次第であります。
夏 : たまには天然のアラスカ鮭も食べましょう
アラスカに夏が近づくといよいよ鮭のシーズンが始まります。大海原で成長した鮭が生まれ故郷のアラスカの河川に一斉にもどってきます。筆者も鮭を買い付けにアラスカの色んな所に出張しました。冬のダッチハーバーとは異なり、夏のアラスカの鮭の現場は天候面では過酷ではありません。ただ問題なのは、ダッチハーバー以上に辺ぴな所がほとんどだという事です。便の欠航は気にする必要はないというか、そもそも定期便などはなく、今にも墜落しそうな糸トンボのようなヘリコプターや、ドアがしっかり閉まっているのか不安になる様なぼろいセスナ機で目的地まで移動しなければなりません。
アラスカの河川に戻る主要な鮭は、紅鮭・銀鮭・白鮭・キングサーモン・マスの5種類です。たとえば紅鮭は、その水揚げの約半分は冷凍され日本に輸出され、あとの半分は缶詰となりイギリス・オーストラリアに輸出されます。紅鮭の子はスジコとなり、全量日本に輸出され主に東北地方で販売されます。皆さんもスーパーで塩紅鮭の切り身をたまに見かけると思いますが、今日ではスーパーで販売されている鮭の切り身はほとんどがチリからの養殖物となってしまいました。生産数量や価格の変動が大きい天然物は、常に格安商材を仕入れなければいけないスーパーのバイヤーにとって扱いづらく、養殖物の方が脂が乗っており一般消費者に好まれるからです。筆者は職業柄いろんな鮭を食べますが、個人的には塩のきいた紅鮭が最も好きです。皆さんもスーパーでアラスカ産の鮭を見かけたら、大自然の味を確認してみてはいかがでしょうか。
秋 : カニ漁は命がけ。高くても納得しましょう。
11月になるとアラスカではタラバガニの漁が始まります。ベーリング海のカニ漁は最も危険な漁業の一つで、台風の墓場と言われるベーリング海の時化た海面に木の葉のように揺れる船上で一辺2m以上のカニ籠を降ろしたり揚げたりしなければなりません。不幸なことにカニ漁では毎年犠牲者が出ます。海に放り出されれば、水温3℃以下では数分と持ちません。映画のパーフェクトストームはアメリカ東海岸の話ですが、ベーリング海でも現実にありうる話なのです。
タラバガニはアラスカで最も高価な水産物で、その総生産量の3分の2以上が日本に輸出されます。アメリカ人もエビやカニは大好きなのですが、ある一定以上の価格を超えるとパッタリ買わなくなり、高級レストランでもメニューから消えてしまうのが通常です。一方、日本人のカニに対する執念は見事なもので、価格が高騰すればスーパーでは販売されなくなりますが、カニ専門レストランチェーンは本業の威信をかけて頑張ります。
アメリカの漁師が命をかけて漁獲したカニを、カニに執念を燃やした日本のカニ専門店で、年に一度は大枚をはたいてみてはいかがでしょうか。水温3℃以下の嵐のベーリング海を思い浮かべて頂ければ安いものです。
なにやら漁獲する話ばかりで、アラスカの水産資源に不安を抱いた方もあるのでは。アメリカは過去の苦い経験や自然保護団体の活動も活発であることから、資源の管理は国家レベルで厳しく実行されております。各魚種の漁獲量は、科学的調査のもとに資源の再生産が可能な状態を維持できるよう設定されます。また、鮭は稚魚の放流事業も盛んに行われております。
養殖も水産タンパクの安定供給には欠かせない事業ですが、大自然の食物連鎖の中で育まれた水産資源を適度に漁獲し、人類が食するという姿は非常に素晴らしい事だと思います。資源の調査・管理、漁獲、加工、流通を通して、各分野に色々な知られざる努力が費やされているという事実を一言付け加え、今回の取留めのない話はおしまいとさせて頂きます。
ということで、アラスカの四季をカヌーで旅しています、とかいうような投稿をしたかったのですが、全く種類の違う話となってしまい申し訳ありませんでした。
(この原稿は10年前にいただいていたものです。申し訳なし。後藤)びぃ どらんく ふぉえばあ
東野 真和(1988年卒)
東京・赤坂。TBSの裏通りは、意外と暗い。その並びにある、とあるバーの話。
ある食品関連会社の若手社員が、修行を兼ねて海外のレストラン経営を任されることになった。仕事帰りに同僚と、ふとそのバーを見つけ、カウンターに座った。カウンターの中には、中年のひげ面の男性が一人。
社員は同僚に、粋がって、ああしよう、こうしよう、と熱くぶつけ、同僚も応じた。
何時間たっただろう。
「おまえら、何を夢みたいなこといってるんだっ」
どなり声は、カウンターの向こうの「ひげ面」だった。「初めての客に何だ」。社員は酔った勢いでかみついた。ひげ面は、蕩々と、経営とは何かを説いた。
「二度ときてやるもんか」。社員は啖呵を切って店を出た。
それから3年半。社員は修行を終えて日本に戻ってきた。海外ではVIPの接待やら従業員教育やら、ひげ面の言う通り苦労の連続だった。
いつかのバーの道を通りかかった。バーはなくなっていた。
「客に喧嘩売るようなバーは、つぶれるだろうな」
ちょっと残念な気がした。通りすぎようとしたら、地下に新しい店ができていた。階段を降りた。
客席に、あのひげ面が座っていた。カウンターの中には、ひげ面の代わりに若い男がいた。
社員はひげ面の前に立つと、直立不動で「すみませんでした。あなたの言う通りでした」と頭を下げた。
ひげ面は、地上を別の店にして、地下に店を作り、息子と交代で店番をしていたのだった。
それからというもの、社員は、その店に3日空けず通い詰めてひげ面と話し込んだ。
社員は、だんだん会社で重い仕事を背負うようになった。大量リストラの先兵になったときも、その苦悩をそのまま伝えた。「いっしょに、別の会社に移ろうかな」と社員が打ち明けたとき、ひげ面は「それは上が決めることだ」と包み込んだ。
四半世紀を経て、社員は会社の幹部になった。いまだに、今では「ひげ爺」になった男に会いに来る。今はただ、馬鹿話をするために――。
私はその話を聞いて、とても幸せな気持ちになった。そして「ひげ爺」に興味を持った。
彼の人生を少しずつ、聞き取っている。新聞記事にするのが目的ではない。ただ、知りたいから。
最近、テレビでも、人の話を聞くだけ、という番組が増えている。昔は「徹子の部屋」くらいいしかなかったのに。
実際あった話というのは、どれだけ作り込んだドラマより心を打つ。取材の原点だな、と思う。
 2011年初漕ぎ(酔っぱらいには関係有りません)
2011年初漕ぎ(酔っぱらいには関係有りません)
オランダでカヌー
小松 雄爾(1989年卒)
オランダに越して来て6回目の新年を迎えた。
仕事は、政府系研究所の研究員。ニッポン労働慣行を離れ、週40時間労働・年休完全消化・年間1800時間労働(=45週間)の暮らしを送っている。ユーロ安と高い所得税(+高い消費税)のせいで、手取りの給料と可処分所得は、あまり多くない。それでも日本の同世代のサラリーマンに比べると、短い労働時間とそれなりの年金が保証されているから、恵まれているといえるか。
さて、オランダといえば運河で有名だ。
オランダ人の祖先が、海面下の土地を干拓してこの地に住み着いた話はよく知られているが、これら干拓地は、低地ゆえ常に洪水の危険にさらされており、雨水や湧出水などを安全に排水するため、網の目のように張り巡らされた運河が遊水地の役割を担っている。
筆者の住む街アルクマール(アムステルダム北方約40km)も、古くは運河の水運で発展した街で、筆者宅のあるマンションのすぐ横手にも運河が通っており、遙かアムステルダム港に面する運河まで、水門を隔てず同水位で繋がっている。
こうなると、カヌーを漕がずにはいられない。
大学を出て以来、数回の初漕ぎやドンドッジ以外、全く漕いでいなかったが、目の前でカヌーを漕いでいる地元民を見ると、久しぶりに血が騒いだ。 アルクマールの町の中心部近くには、カヤックを貸し出す店があり、何度か利用した。
最初の数回は、カヌー部時代の感覚を思い出すのに四苦八苦したが、回数を重ねると、時間貸しでは物足りなくなる。せっかくだからもっと遠くまで漕いでみたいのだが、返却時刻・閉店時刻そして、帰路に残しておく体力を考えると、どうしても心残りをしながら引き返さざるを得なかった。
そんなわけで昨年5月、なけなしの小遣いをはたいて、ついに自艇を買った。方向舵なしのポリエチレン製で底は真っ平ら、学生の頃はバカにしていたツーリングカヤックであるが、40半ばのオッサンには、こんなもんで丁度いい。安物のゴルフセットよりチョット値は張るが、ゴルフのようにプレイ料金はかからないので、ゴルフよりは安上がりのはずである(というのが、妻への言い訳である)。
親切な近隣の知人に倉庫のスペースを一部貸してもらい、そこから運河の乗艇口まで200メートルほど、折り畳み式の台車に乗せて引きずっていく(台車は乗艇中はカヌーに収納する)。レンタルと違い、返却時刻や営業時刻を気にせず乗れるのは実に気楽である。
日曜日に握り飯を用意して遠出をするだけでなく、平日の夕方にフラっと漕ぎに出ることもできる。5時15分退勤・5時40分帰宅・6時乗艇開始・8時終了が、典型的な平日の乗艇だ。北樺太に相当する高緯度とサマータイムのおかげで、初夏は夜10時過ぎても明るいのもありがたい。
 観光用運河クルーズ船と並漕する筆者。
観光用運河クルーズ船と並漕する筆者。
平均的に、2時間で12キロ、今までのところ1日最長は32キロである。来シーズンはもう少し遠くまで行ってみたい。GPS付き携帯電話で、Google mapに航跡を記録していけるのも、また、一つの楽しみである。
カヌー部にいたころは、まさか自分が将来オランダで働くとは夢にも思っていなかったが、こうして大学での経験を日常の趣味として生かせるようになったのは、まさに僥倖、もうしばらくこの暮らしを続けるのも悪くない。
さて、みなさんも、オランダ・アルクマールで日曜日を過ごせる機会があれば(3月~ 9月・秋冬は寒すぎてムリ)、いっしょにカヌーを漕ぎませんか?ただ、レンタル店には左固定のパドルは置いていないので、捻り角なしのパドルで頑張ってください・・・(右固定の人は問題ナシ)
 10年前の写真ですが此処もカヌーで行けるはず(後藤)
10年前の写真ですが此処もカヌーで行けるはず(後藤)
1994年夏、いちばん静かな湖
鳥井 浩司(1995年卒)
そのレース、600mを過ぎた辺りで早くも私は自分の「限界」を感じていた。それまでに味わった事のない苦しさであった。2艇身前の先頭には、我々4回生の多くにとっては引退試合となる関学選で、最後に頭角を現した神大岩城、1艇身前にはジュニアあがりでは関西最速の同志社白賀、横には当時関西最強の立命館片木がいた。私はその状況を上手く解釈出来なかった。ただ、このペースではゴールまでもたないと危惧した。
遠のく意識の中で、私の耳元に微かに同志社応援団の太鼓の音色が響いた。私はそれを自分に向けられた応援だと信じた。既に未知の世界であった。
私は、大学生活の大半をカヌーに打ち込んだ。まだ穏やかな太陽の光を頬に受けながら、シルクの様な水面を切り裂いて進む朝練の爽快感を忘れない。しかし学生として、ややバランスを欠いていた事は否めない。引退後の一年半できりりと弓を引いたものの、そこから放たれた矢は頼りなく、その度に私は弦をより強く張り直して来た。
700m付近で、立命館片木のパドルが扇風機の羽根の様に勢い良く回り始める。私はそれを横目に見ながらラスト100mに来ても尚、決心がつかなかった。残りの体力を確信したラスト50mで漸く私はスパートをかけ、4位でレースを終えた。優勝した片木とは約1艇身差の、4分間弱の戦いであった。ラスト100mでギアを入れ直せば、また違った展開もあったろうか。ただ、全てを捧げて挑んだレースで完漕しゴールすることだけは、絶対に成し遂げる必要があった。力を出し切ったと思っている。
人は何かをイメージし、努力を重ねれば、自ずとそれに近付くものだ。私は社会人となってから、2度転職した。新宿の超高層ビル街で、建築の仕事をするという、高校時代に描いた目標は実現した。ただ、プロパーではない私は、FA選手よろしく結果のみが判断基準となる環境に身を置いてしまった様だ。今の私は、速いか遅いかだけの陰影のない2次元の世界に生きている・・・。そんな想いに囚われる時、あの日の私が、今の私の背中を押してくれるのである。
近 況
古荘 貴也、えみ(2002年卒)

私は西宮でアウトリガーカヌーを始めて5年になります。アウトリガーカヌーとは、南の海で使われていた船で・・・説明しても伝わりにくと思うので、乗ってみるのがお勧めです。 波に乗ったり揉まれたりして気持ちいいですよ。 船もかっこいいです。現役生も息抜きに一度乗りに来てはどうでしょう。あっさり抜かないでね。いろんな人が集まって漕いでます。みんなでハワイの大会に出るのが目標です。楽しみです。
 (こちらからお願いして提供いただきました。)
(こちらからお願いして提供いただきました。)
妻のえみは、夏に女児を出産し育児に奮闘中です。子供を持って初めて親の有り難さがわかりました。毎年、初漕ぎには参加していましたが、親戚行事と重なりこの数年は行けずに残念です。
また、何かの機会にお会い出来る日を楽しみにしています。
河奴会(関西)恒例のゴルフコンペ
小内 勝雄(1967年卒)
関西OB会は、何時のころから新年会と夏冬のゴルフが懇親の場とし て恒例化されています。
| 河奴会愉 | 河奴会は愉し |
| 離別幾星霜 | 離別して幾星霜 |
| 夏時楽野遊 | 夏時に野遊を楽しまん |
| 人生顔色現 | 人生は顔色に現れ |
| 今日態悠悠 | 今日の態は悠々なり |
瀬田川を離れ随分な年月が流れましたが、会えばすぐにあの頃に戻り 談笑しながらのゴルフ。各々の生き様は顔に現れるものです。参加の 皆様の姿は自信に溢れた悠々たるものでした。(H21・7城陽CC)
 中本(S46) 古川(S46)
清野(S45)矢部(S44)青木(S44)池田(S44)新居(S45)
有山(S44)小橋(S43)小内(S42)石倉(S41)
中本(S46) 古川(S46)
清野(S45)矢部(S44)青木(S44)池田(S44)新居(S45)
有山(S44)小橋(S43)小内(S42)石倉(S41)
OB・OG会 都 内 周 航
 日本橋、本来は風情のある作りの橋です。(森君か早川君の提供)
日本橋、本来は風情のある作りの橋です。(森君か早川君の提供)
 聖橋、右はJR御茶ノ水駅、緑の掘り割りに感激
聖橋、右はJR御茶ノ水駅、緑の掘り割りに感激
四万十川はちょっと遠いという方、近場でも新鮮な発見のある周航が楽しめます(とはいえ長野から来てくれる人達がいないと成立しない周航ではあるのですが)。上の写真は3年前です。今年はどこを漕ぎましょうか? 後藤
(平成20年の神田川・日本橋川巡りと 平成21年の隅田川下りの詳細はWEBでご覧になれます。:WEBマスター)
現役寄稿文
私の新勧隊長時代、主将の経験について
寺下 友樹(4回生、前主将)
カヌー部OB・OG、現役の皆様、新年明けましておめでとうございます。
2010年度主将を務めさせてもらいました寺下です。河奴が復刊されると聞いて私も大変嬉しく思います。早速ですが、僭越ながら私の新勧隊長時代、主将の経験についてお話したいと思います。
私がカヌー部に入部したころは確か部員は10人足らずでした。先々代の橋口主将、先代の白波瀬主将からはいかに部員を増やすことが大事か教わり、また私自身も一回生のころは総部員が100人超にもなる強豪ボート部に所属していた経験からも、カヌー部の部員を増やすことは至上命題であると 考えておりました。そこで三回生で新勧隊長を務めさせてもらった時は必ず多くの部員を入れてやると誓いました。 私(というより私達)がとった戦法は単純です。とにかく一人でも多くの新入生の連絡先を手にいれること。連絡先を手に入れたら、しつこく連絡をとり瀬田川へ一人でも多く連れてくること。この二点です。
私たちカヌー部の活動拠点は大学から離れた場所にあり、多くの新入生にとって琵琶湖は他県で遠いからそんな場所に通い続けるのは無理だと、はなからカヌー部に目を向けてもらえないのが痛いところです。しかしながら、一度でも瀬田川に来てもらえれば、カヌーの面白さ、また私達部員同士の遠慮ない信頼関係に惹かれてきっと入部してくれるだろうという自信がありました。
実際入部してくれた部員の中には「カヌー部なんてまったく興味がなかったが先輩の勧誘がしつこすぎて、瀬田川に行かなければえんえんと電話がかかってくる」としぶしぶ琵琶湖に来たところ、カヌーの魅力に惹かれて入部し、ジュニアカナディアンで日本一にまでなってしまったのですから、勧誘の時は「こいつは入りそう、こいつは来ないだろうな」などと選り好みして勧誘はしないことが大切だと実感しました。
結果、私が主将に就任した頃は、部員は24人に、その次の年には37人にまで部は大きくなりました。
次に主将経験についてお話しいたします。
私が主将に就任してから、常に念頭においていた言葉があります。「組織化」「視覚化」です。これから大所帯になっていくであろうカヌー部。常に発展し、実績を残して行くにはより細かな役割分担、選手の育成計画が必要です。今までの主将、副将、主務、会計に加えて、艇庫生活大臣(艇庫生活での秩序を保つ、または改善)、艇庫一階大臣(艇管理、一階の整理整頓)、栄養管理大臣(体つくりのため選手に定期的に栄養学についてレクチャー)、筋力トレーニングコーチ(筋トレメニューを考え、筋トレの大切さを部員に自覚させる。必要があれば定期的にレクチャーも行う。前年度は私が兼任)など新しい役割を設けるなど組織化し、筋トレの際は定期的に最大筋力測定会を行う、冬季乗艇自主練習に関しては乗艇した距離をグラフ化し部員間の競争意識向上を図る、定期的に体重測定、何をいつ食べたのか各自部員にメモをとらせ、栄養学マネージャーにカロリー計算をしてもらいアドバイスを受ける、また新勧はどういった手順でやるかを書類にまとめ引き継ぐ、と言った「視覚化」。
これら役割や定例行事をつくってしまえば 「誰が」 主将になっても基本的には機能する「枠組み」であり、このような「枠組み」をつくることが、継続的に部が成長するために、また冬の時代(部員が一人になってしまうような時代)を繰り返さないためにも必要であると考えています。こういった枠組みに加えて、部全体としての方向性、目標がまとまり、各部員が勝利や早さへのこだわりを高いレベルで維持できれば必ずや強い京大カヌー部になれると信じています。
長くなりましたが、最後に現役のみなさんに一言。
どんなにつらくても「辞める」ことだけはしないで下さい。終わってみれば、辛い思い出も素晴らしい思い出へと姿を変えます。それはきっと辛いと思いながらも頑張った結果、成長した自分を体の芯から実感できるようになるからでしょう。
また「京大カヌー部」は競技だけがすべてではありません。すでにできたユニークで素晴らしい仲間達との絆についてもう一度考えてみてください。 また春に会いましょう!
4年間の部活を終えて
小倉 祥子(4回生、前マネージャー長)

現在カヌー部は選手26名マネージャー4名で活動しています。12月の寒さに耐えて、来シーズンを見据えて選手一同練習に励んでいます。そんな中、マネージャーも選手と同じ思いを胸に、共にこの冬を過ごしています。現在のマネージャーの主な仕事は、体作りのサポートで、栄養バランスを考えた食事を作ったり、筋トレや、体重管理を行ったりしています。さらに練習の雰囲気を盛り上げるため、声かけも意識的に行っています。基本的なマネージャーの仕事は確立し、更にできることはないかと現役マネージャーたちは日々いろいろなことに挑戦しています。

しかし、私が部活に入部した4年前は選手8名の小さい部活で、まだまだマネージメントという考えは根付いていませんでした。私自身もビデオ撮り、食事作りなどの与えられた仕事をこなすだけで、カヌーについても詳しくなろうとしませんでした。ただ、このころの部活はとてもアットホームな空間で、休憩時間に部員と話したり漫画を読んだりするのが楽しく、それはそれで良い思い出です。

2回生になって少しずつ意識が変わり始めました。初めての新歓を体験したときのことです。最初は何も分からず、自分自身の目的意識も低く、どうしてこんなしんどいことをしなければいけないのかと思っていました。しかし話し合いや、新歓を通して、先輩たちが部活を大きくし、部活を強くしようと思っていることが伝わってきました。更に、この頃から部活の仕事を任されるようになり、実際的に部活に関わる機会も増えました。仕事に対して先輩から叱られたこともありました。これらをきっかけにして、マネージャーとしての自覚ができたと思います。この部活において自分は何ができるだろうか、少しづつできることから変えて行こうと考えるようになりました。その結果、まず最初に改善したのは食事でした。特に栄養バランスを考え品目を増やしたり、様々な種類の野菜を使ったりしました。


3回生ではマネージャーの増員が不可欠だと考え、新歓でのマネージャー勧誘に力を入れました。今まではマネージャーの人数が少なく、食事の支度と練習のサポートを同時に行うのが困難だったからです。勧誘の甲斐あって、マネージャーが増え、マネージャーの仕事を充実させることができました。
ただ良いことばかりではなく、悩みも増えました。一番大変だったのが、プレーヤーとマネージャーの距離感でした。特に夏の大会の時期ではマネージャーは早朝から、深夜まで働きづめです。部員を最優先にしなければいけないため、お風呂に入るのも深夜になってしまい、かなり体力的にも精神的にも辛くなっていました。選手も自分のことで精一杯な中、なかなかマネージャーとして部活を思いやれることができませんでした。また後輩マネージャーも初めての夏で、マネージャー長としてその面倒を見ながら仕事を回すことに疲れていました。部活におけるマネージャーの役割、関わり方など全体を含めた観点から部活を考えらえず、自己嫌悪に陥っていました。
それでも持ち直せたのは、大会が終わって、選手が来年のシーズンを見据えて頑張っているのを見たときでした。今までの自分の小ささや、無能さに嫌けが指しましたが部活全体で来年に向けて頑張ろうという思いが一致し、また前向きに考えることができました。
最後の年には、最上級生として全体をまとめなければいけません。その中で、全員で勝ちに行くというのが部の目標でした。マネージャーとしては、今までの仕事に加え、もっとメンタル面でのサポートができないかと考えました。そこで練習中や筋トレの声かけなど練習自体の気分の盛り上げを意識的に行う様にしました。 また、最後の夏が近くなると、部活に私ができる最大限のものを残したいと考え始めました。そこで理学療法士の卵としても部活に関わろうと考え、筋トレやストレッチの改善、漕ぎの研究などにも関わりました。早い選手の漕ぎを研究し、それに基づいて、ストレッチ、筋トレプログラムを立てました。

そして迎えた最後の大会、初めてインカレの表彰台に選手が立ってくれました。正直これは本当にうれしかったです。体も逞しくなって、ライバルに気持ちで負けることなくゴールする選手の姿は頼もしかったです。入部したときは沈するかどうか不安になりながら漕いでいた選手たちの成長を目の当たりにし、選手たちの頑張りが結果につながったことに自然と涙が出てきました。自分がやってきたことが無駄じゃなかったと感じることができました。
引退して思い返してみると、私はマネージャーとしてというより、少し母親に近い気持ちで部活に関わっていたかも知れません。選手1人1人がかわいくて、みんなが頑張ってるから、充実した1年が過ごせるよう、それを支えたいというのが私のモチベーションでした。

今の部活は先輩たちの思いが息づいて、それが徐々に形になってきていると感じます。部員も増え、部活としての体制が整った今、マネージャー達には部活への誠実さ、仕事への自信、そして謙虚さ、思いやりなどいろんなものが求められると思います。大変なことが多いと思いますが、これからもマネージャーとプレーヤーが対等で全員で勝利に向かっていくような部活であって欲しいと思います。そしてマネージャーもプレーヤーも含めた部員全員が、部活を通して何かを学び、きらきらした大学生活を送れることを願っています。
琵琶湖周航顛末記
小野 裕貴(4回生、前副将)
小松 峻也(4回生、前主務)
はじめに
琵琶湖周航は隔年で行われるので、私達は引退までに2回の琵琶湖周航を体験したことになります。今回の顛末記ではその両方の出来事を交えつつ、各日程・地点での思い出を辿りながら書いていこうと思います。
1日目:カヌー部艇庫~真野浜~近江舞子

全員集合して開会式の後、艇庫から旅立ちます。開会式では開会の言葉、男子部員のダイナミックな飛び込み等で盛り上がりました。真野浜までは大きく荒れることも無かったのですが、慣れてきていない部分も多く、艇の細かい故障が相次ぎ、ここで修理のスキルを磨くことになりました。
 (カヌー組を見守る自転車組)
(カヌー組を見守る自転車組)
全体として、カヌー組は昼食前2組、昼食後2組の4組で交代して回します。また、交代後はカヌー組を沿岸から見守る自転車組として、写真を撮ったり、沿岸の町並みを楽しんだりしながらカヌー組と行動をともにしました。車組は休憩地点に先回りして、食事の準備やテントの設営をします。
1日目の夕方から波が出始め、時には転覆することもありましたが、特に大きなトラブルも無く、ほぼ時間通りに宿泊地の近江舞子に到着することが出来ました。夜にはレクリエーションや、酒を酌み交わしての宴会などをして、水上での疲れを癒します。
2日目:近江舞子~琵琶湖こどもの国~マキノサニービーチ
朝は5時半ごろから起床し、質素な朝食をとります。ちなみに、夜の寝床はテントは混雑していると思った人が多かったらしく、車や野宿(!)をしている人が大半でした。琵琶湖周航は晴れた日がほとんどだったので、綺麗な星の下で野宿をすることが出来ました。
2日目のハイライトは白髭神社です。午前中に自転車組・カヌー組みだった人たちは、交代場所の白髭神社でカヌーに乗って鳥居をくぐりました。
ここは水もとても澄んでいて、とても綺麗でした。休憩時間に泳いで遊んだこともいい思い出です。
2日目の宿泊地、マキノサニービーチは宿泊地の中で最北端であり、水も冷たいですが最高に綺麗でした。ここでカヌーを漕ぐのはまたとない経験でした。途中の釣具店で釣具を買った人や銛を買った人は魚を獲ったりして楽しんでいました。上手な人たちは何匹も捕まえていて、すごいなぁと感心させられました。
ここの周囲には大きな町が無いこともあり、夜には浜辺に寝そべって何個も流れ星を見ることが出来ました。他には連れ立って散歩に行く人、宴会に興じる人など、思い思いに夜を楽しんでいたようです。
3日目:マキノサニービーチ~琵琶湖最北端~民宿「中茂」

マキノサニービーチから最北端に向かって艇を進めます。ここで苦労するのは自転車組です。立ちはだかるのは「奥琵琶湖パークウェイ」。いつもなら自転車組がカヌー組を待つのですが、約10キロの山道を抜けてカヌー組を追います。
しかし、頂上ではすばらしい展望が僕らを迎えてくれました。
最北端でお昼を頂き、琵琶湖の最も澄んだ部分を漕ぎ進みます。こんな環境でカヌーの練習ができたらすばらしいだろうなぁと思いました。

この日は毎回琵琶湖周航でお世話になっている、民宿の「中茂」さんのところに泊まります。
この夜はバーベキューをして、みんなで盛り上がりました。中茂のおじちゃん、おばちゃんに気前よく電灯やコンロを貸して頂き、とても快適にバーベキューを楽しむことが出来ました。感謝です。
久しぶりの布団ということで気持ちよく早めに寝る人も居る中、宴会が盛り上がりすぎて夜遅くまで騒ぐ人など、それぞれの楽しみ方をしていました。
4日目:民宿『中重』~円覚寺~マイアミ浜オートキャンプ場

朝、中茂で全員集合して記念撮影をしました。これは毎回の記念行事です。中茂のおじちゃん、おばちゃん、いつまでも元気でいてください。

4日目は追い風で下りということもあって、最長の距離を漕ぎます。波も穏や かで漕ぎやすく、カヌーはスイスイ進みます。
自転車組は岸沿いにカヌー組み追いかけつつ、応援歌などを歌ってカヌー組を励ましました。長い距離を漕ぐのはやはり大変です。

この日の昼間の休憩場所は公園で、みんなで遊具をつかって子供に返ったかのように遊びまわりました。とても楽しかったです。
夜はきちんと整備されたキャンプ場で、いつもの野宿ではなく、シャワーや炊事場などを使ったきちんとした"キャンプ"を楽しみました。
5日目:マイアミ浜オートキャンプ場~琵琶湖博物館~カヌー部艇庫

この日は朝早くから漕ぎ始めたこともあり、波も無く穏やかな中を漕ぎ進みます。マイアミ浜から琵琶湖大橋まで一気に漕ぎ進めました。しかし、交代場所の琵琶湖博物館までは藻が多く、進むのにとても苦労しました。
近江大橋を越えてからは自分の場所に帰ってきたなぁ、という感じでラストスパートをかけて、ゴールのカヌー部艇庫にたどり着きました。

ゴールしてからは閉会式を行い、皆で健闘を称えあいました。男子部員達飛び込んだりしていました。終わったあとはやはり何かをやり切った達成感を感じることが出来、素晴らしい体験をさせてもらったなぁと思いました。
・最後に
これで琵琶湖周航顛末記はおしまいです。5日間という時間は長いようで短く、思い返せばあっという間に過ぎてしまったような気さえします。きついこともありましたが、気心の知れた仲間と乗り越えることでかけがえの無い経験にすることが出来ました。
主将あいさつ
竹部 翔馬(3回生 主将)
OB・OGの皆さまこんにちは。9月から主将を務めております竹部です。現役部員として、復刻した河奴に投稿させていただけることに感謝いたします。
近年のOB連絡をご覧になった方はご存じかと思いますが、ここ2,3年で我々京大カヌー部はその規模を大きく拡大し、人数はかつての黄金時代にまた近づきつつあります。すべては、廃部の危機にあっても投げ出さず、地道に粘り強い勧誘活動を継続してくださった先輩方のおかげです。そのDNAを我々現役部員もしっかりと引き継ぎ、強くて大きな京大カヌー部を作るべく今後も努力していく所存です。
また、競技面でも着実にその力をつけていると実感しております。2010年には久しぶりのインカレ入賞(小松・岡本組・C2・10,000m第5位)がありました。2009年には貴重な中・高カヌー経験者(柴田康弘・カヤック)を迎え、カヌー競技未経験者が多数の我が部にとっての大きな財産となっています。また、OBの皆さま方の支援もあり、コーチとして日本代表の鈴木康大選手にもレクチャーしていただくなど、技術面・肉体面においても大きく変わろうとしています。さらに、青木謙治先生のお力添えによる大学側の支援やOBの皆様のご寄付により最新のペア・フォア艇を手にしていることなど、現在京大カヌー部ではカヌー競技をするにあたって絶好の環境が用意されつつあると言えるでしょう。
私が入部した当時、10名程度の規模であったこの部が、今や瀬田界隈では一、二を争う大規模チームにと成長したことを大変誇らしく思っております。一方で、変化する環境、部員の多様性などに対応するべく、様々な改革が迫られている節目の時期でもあると痛感しております。そんな中、我々現役部員が各々の想いをぶつけ合い、皆が納得するまで議論し、創り上げた「京大カヌー部の理念」があります。
- 一、 全員が主体的に部に関わる
- 一、 部活動を通して人間的に成長する
- 一、 集団生活を通して自律する
- 一、 切磋琢磨して、全員で勝ちを目指す
- 一、 互いを尊重する
- 一、 文武両道
個々人の個性を尊重しながら、これらの共通理念を常に意識し、私たちは日々練習に取り組んでおります。関西では依然として覇権を握っている立命館大学・関西学院大学に追いつき、追い越すことは一朝一夕には達成されません。しかし、京大カヌー部は、現在とても勢いのあるチームです。この勢いを絶やさず、さらなる飛躍を求め日々部員一同切磋琢磨して参りますので、今後ともどうぞご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
 2010年7月10日艇庫にて(継ぎ目に当たった人、ごめんなさい)
2010年7月10日艇庫にて(継ぎ目に当たった人、ごめんなさい)
京大カヌー部 2010年 戦績と活動
京大カヌー部 2010年 戦績と活動はこちらのpdfファイルをご覧ください
2011年京都大学体育会カヌー部・部門別目標
| 【男子カヤック部門】 |
| 関西学生選手権 |
| カヤック部門3位K-1 RELAY・K-4 3位 |
| JK-1,JK-2表彰台 |
| 全日本学生選手権 |
| ポイント奪取 |
| JK-1,JK-2表彰台 |
| 【カナディアン部門】 |
| 関西学生選手権:カナディアン部門準優勝・C4優勝 |
| インカレ:C4表彰台 |
| 【女子カヤック部門】 |
| 関西学生選手権・女子総合3位 |
| ジュニアメダル |
| 【マネージャー部門】 |
| 皆の目標達成を常に意識、プレーヤーの心の支えとなる |
2010京大カヌー部現役部員紹介
☆4回生☆
| ① | 小倉祥子(おぐらしょうこ) | ② | マネージャー |
| ③ | 前会計・マネ-ジャー長 | ④ | 医学部人間健康科学科 |
| ⑤ | 千葉県・千葉東高校 | ⑥ | |
| ⑦ | 男だらけの時代に入部し、以来カヌー部を支え続けてきたマネ ージャー。彼女なしに今のカヌー部の姿はありえない。 てきとうな性格で興味のない話は聞いてない。 | ||

| ① | 小野裕貴(おのゆうき) | ② | カヤック |
| ③ | 前副将・カヤック長 | ④ | 工学部工業化学科 |
| ⑤ | 熊本県・熊本高校 | ⑥ | PLASTEX・MIDAS |
| ⑦ | カヌー部が誇るド変人。彼の手によって艇庫に眠っていた幾つも の艇が修理され試合で活躍している。これらがなければ艇不足。 場の雰囲気を一瞬にしてフリーズさせる特殊能力をもつ。 | ||

| ① | 小松峻也(こまつたかや) | ② | カナディアン |
| ③ | 前主務・カナディアン長 | ④ | 工学部地球工学科 |
| ⑤ | 岐阜県・岐阜北高校 | ⑥ | NELO・VanquishⅡ |
| ⑦ | カヌー、筋肉、勉強、言動などあらゆる面で変態。ラストレース、イ ンカレC2・10,000mで岡本とともに5位入賞を果たされた。院試免 除で大学院に進学される | ||

| ① | 寺下友樹(てらしたゆうき) | ② | カナディアン |
| ③ | 前主将 | ④ | 経済学部 |
| ⑤ | 兵庫県・六甲高校 | ⑥ | PLASTEX・DOMINATOR |
| ⑦ | 2回生時入部ながら、誠実で周囲を明るくする人柄でチームを 引っ張って下さった主将。持ち前のコミュニケーション能力と下○ タを駆使し?某人気企業に内定。 | ||
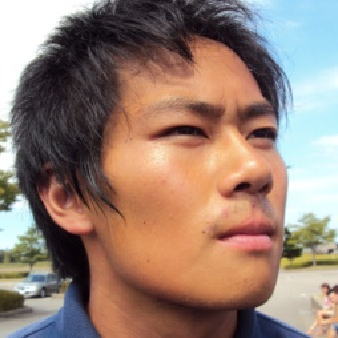
☆3回生☆
| ① | 黒河宏太郎(くろかわこうたろう) | ② | カナディアン |
| ③ | 主務・カナディアン長 | ④ | 法学部 |
| ⑤ | 愛媛県・今治西高校 | ⑥ | PLASTEX・OLYMPIAⅡ |
| ⑦ | 絶対的な権力でカナディアン部門を率いる。カヌーにとても真面目で、勉学を限りなくそぎ落としカヌーに注いでいる。絶賛就活中である。OB・OGの皆さんよろしくお願いします。 | ||
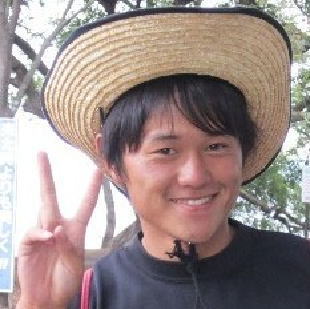
| ① | 竹部翔馬(たけべしょうま) | ② | カヤック |
| ③ | 主将・トレーナー | ④ | 法学部 |
| ⑤ | 神奈川県・ACS Hillington International School(英国) | ⑥ | PLASTEX・OLYMPIC WARRIOR |
| ⑦ | イギリス帰りの帰国子女であり、我らが主将。現在、京大カヌー部を強くするため様々な事を取り入れてくださっている。前主将と同じく、下○タが大好き。 | ||

| ① | 松浦耕介(まつうらこうすけ) | ② | カヤック |
| ③ | 学連・カヤック長 | ④ | 経済学部 |
| ⑤ | 広島県・修道高校 | ⑥ | PLASTEX・MIDAS |
| ⑦ | 次期学連理事長で、学生カヌー界の頂点に立つ!真に文武両道を実践している。三回生にして、もはや京大にはほとんど行く必要がない。重責を背負う彼は、奥田をいじめてストレス発散。 | ||

☆2回生☆
| ① | 安藤智史(あんどうさとし) | ② | カヤック |
| ③ | トレーナー・艇管理大臣 | ④ | 工学部地球工学科 |
| ⑤ | 香川県・観音寺第一高 | ⑥ | ヒカリ・タイガー |
| ⑦ | 瀬戸内の島出身で独特のイントネーションを持ち皆に真似される。 トレーナーとしてトレーニングの向上を図る一方、艇管理大臣とし て部所有艇と艇庫1階の管理を行う。 | ||

| ① | 岡本弘晃(おかもとひろあき) | ② | カナディアン |
| ③ | 副将・艇管理大臣 | ④ | 工学部物理工学科 |
| ⑤ | 滋賀県・膳所高校 | ⑥ | NELO・VanquishⅡ |
| ⑦ | 鋭い観察眼と頭脳で奥田をこき下ろす。2回生にしてインカレペア 5位入賞を果たした。しかしPOLITEで、まだまだ上を目指す。 副将としてチームを引っ張る。 | ||

| ① | 海野大和(うんのやまと) | ② | カナディアン |
| ③ | 副務 | ④ | 農学部森林科学科 |
| ⑤ | 静岡県・静岡聖光学院 | ⑥ | PLASTEX・OLYMPIAⅡ |
| ⑦ | 副務として数多くの仕事をこなす。部活に関しては忌憚なく意見 を述べる。やや一貫性がないのが玉に瑕。ラグビーで鍛えた体を 速さにつなげられるまであと少し。 | ||

| ① | 奥田長武(おくだおさむ) | ② | カナディアン |
| ③ | 艇庫生活大臣 | ④ | 法学部 |
| ⑤ | 兵庫県・洛南高校 | ⑥ | NELO・Scorpion |
| ⑦ | 艇庫の美化を担う生活大臣。毎乗艇後、船台漕ぎに向かう彼の姿 はチームを支えてきた。ロースクールを目指し六法系科目とも 格闘している。 | ||

| ① | 小野淳(おのあつし) | ② | カナディアン |
| ③ | 新歓大臣 | ④ | 経済学部 |
| ⑤ | 福岡県・京都高校 | ⑥ | PLASTEX・DOMINATOR |
| ⑦ | 新歓大臣と腹筋大臣を兼ねる、カナディアン部門限定のトレーナー。カナディアンに腹筋を課す。部員を深く観察しいじり倒す。ジュニア時代全種目で優勝した男が3年目に懸ける。 | ||
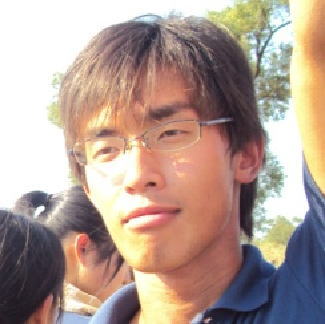
| ① | 小林美緒(こばやしみお) | ② | マネージャー |
| ③ | マネージャー長 | ④ | 法学部 |
| ⑤ | 東京都・St.Mary'sSchool,Calne(英国) | ||
| ⑦ | 従来のビデオ・タイム撮りだけではなく、部員の毎日の食事をチェックして栄養指導を行う「栄養分析」にも精を出す。毎週の幹部ミーティングでも意見をしっかり述べてくれる、陰の大黒柱。 | ||

| ① | 柴田康弘(しばたやすひろ) | ② | カヤック |
| ③ | 副将 | ④ | 工学部工業化学科 |
| ⑤ | 愛知県・豊田西高校 | ⑥ | NELO・Vanquish |
| ⑦ | 中学からカヌーを続けている貴重な経験者。技術や筋力で京大カヤックを牽引する。お茶目な一面もあり、真の意味で楽しめる新しい練習を模索中。爽やか、しかしひどい下○タが多い。 | ||

| ① | 壺井佑夏(つぼいゆか) | ② | カヤック |
| ③ | 副務・学連 | ④ | 工学部物理工学科 |
| ⑤ | 香川県・高松高校 | ⑥ | NELO・Moskito65 |
| ⑦ | 意外にも学連・副務として仕事をしっかりこなす働き者。ただし 滑舌が悪く何を言ってるのかわからない。2010京選優勝の女子 カヤックのエース。瀬田は制して、今年は関東勢に襲いかかるか。 | ||

| ① | 平野桂太郎(ひらのけいたろう) | ② | カヤック |
| ③ | 広報 | ④ | 農学部応用生命科学科 |
| ⑤ | 愛知県・東海高校 | ⑥ | HIKARI・レーザーMAX |
| ⑦ | はっきり言って普段はやる気がまったく感じられない。しかし、練習中相手と競り始めるととんでもない力を出す。スタートダッシュはピカ一。 | ||
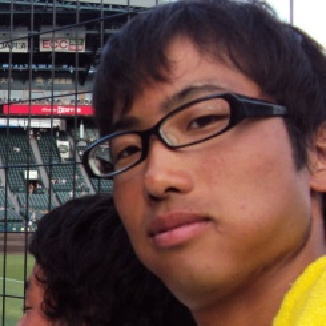
| ① | 横井郁(よこいかおる) | ② | カヤック |
| ③ | 女子カヤック長 | ④ | 総合人間学部 |
| ⑤ | 兵庫県・白陵高校 | ⑥ | ヒカリ・レーザーX |
| ⑦ | HEAD OF THE SETA(毎年11月開催の約7kmのロングレース)の二連覇を達成した瀬田の女王。女子カヤック長として、女子部門をゼロから作り上げてゆく。 | ||

☆1回生☆
| ① | 浅田温哉(あさだあつや) | ② | カヤック |
| ③ | ④ | 法学部 | |
| ⑤ | 愛知県・東海高校 | ⑥ | ヒカリ・レーザー |
| ⑦ | 原田(の鼻毛)をこよなく愛するマッチョマン。腕漕ぎ(に見える)だが、筋肉で艇を進める漕ぎですでに先輩を食い始めた。特技は、麻雀のイカサマをして天和・大三元を出すこと。 | ||

| ① | 伊藤光祐(いとうこうすけ) | ② | カナディアン |
| ③ | ④ | 工学部物理工学科 | |
| ⑤ | 広島県・広島大学附属福山高校 | ⑥ | ヒカリ・ガンマ |
| ⑦ | 今年の一回生のなかで最初に入部宣言したパイオニア。癒し系。ジュニア時代は勝野とのペアで関学選・インカレともに優勝。しかし、怪我を負い現在は再起を誓いリハビリ&筋トレ中。 | ||

| ① | 岡原拓馬(おかはらたくま) | ② | カナディアン |
| ③ | 応援団長 | ④ | 工学部物理工学科 |
| ⑤ | 愛媛県・南宇和高校 | ⑥ | ヒカリ・ガンマ |
| ⑦ | 入部当初から頭角を現した天然ボケタイプ。彼は、今年度、数々の流行語を生みだし艇庫の雰囲気を常に明るくしてきた。カヌーでは、さらなるレベルアップを期待。 | ||

| ① | 勝野友之(かつのともゆき) | ② | カナディアン |
| ③ | 学連 | ④ | 工学部物理工学科 |
| ⑤ | 京都府・南陽高校 | ⑥ | ヒカリ・ガンマ |
| ⑦ | 先輩から言われたことをきちんとこなす真面目で腹黒い一回生。ジュニア時代はシングル準V、ペア優勝。体が大きく、漕ぎの形も良い。2年目どこまで行けるか。 | ||

| ① | 後藤大輝(ごとうひろき) | ② | カナディアン |
| ③ | ④ | 理学部 | |
| ⑤ | 岐阜県・岐阜高校 | ⑥ | ヒカリ・ガンマ |
| ⑦ | 理学部の中の理学部。変態。カヌーと数学と麻雀を同じぐらい愛するが、語学の単位には愛されていない。しかし意外と根は真面目で普通である。これからの伸びに期待。 | ||
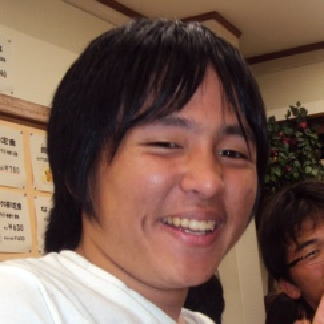
| ① | 佐藤那美(さとうなみ) | ② | カヤック |
| ③ | ④ | 薬学部薬学科 | |
| ⑤ | 香川県・高松高校 | ⑥ | 造研・カッター |
| ⑦ | 3行ではとても表せそうにない。中年の男性の様であったり、はたまたアニメ文化に精通していたりと様々な顔を持つが、真面目で熱い一面も。 | ||

| ① | 白川瑞紀(しらかわみずき) | ② | マネージャー |
| ③ | ④ | 法学部 | |
| ⑤ | 福岡県・京都高校 | ⑥ | |
| ⑦ | 最近増えているとかいうオタクとよばれる部族。選手へのエールがアニメ声・・・。しかし練習中ビデオを撮りながら応援する彼女の声は練習中よく通り、部員を励ます。 | ||

| ① | 原田和樹(はらだかずき) | ② | カヤック |
| ③ | ④ | 工学部工業化学科 | |
| ⑤ | 京都府・東大寺学園 | ⑥ | ヒカリ・タイガー |
| ⑦ | 部内有数の愛されキャラ(笑)。音楽と地図を愛するため、車に乗ると実に騒がしくなる。謙虚過ぎて自らの発言をすぐに撤回する。一回生にまでも敬語を使ってしまう。 | ||
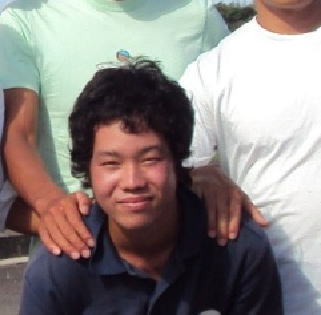
| ① | 馬場翔子(ばばしょうこ) | ② | カヤック |
| ③ | ④ | 理学部 | |
| ⑤ | 京都府・堀川高校 | ⑥ | 造研・カッター |
| ⑦ | 女子部屋の入り口で勉強をし続けるまじめな京都っ子。つまらない話に対しては、たとえ相手が先輩でも恐れることなく「ふ~ん…」と流し、黒河さんを困らせる。 | ||

| ① | 吹野由佳(ふきのゆか) | ② | マネージャー |
| ③ | ④ | 工学部建築学科 | |
| ⑤ | 東京都・立教女学院 | ⑥ | |
| ⑦ | おっとりながらも茶目っ気たっぷりないたずらっ子。毎合宿マネージャーとしてビデオを撮り、栄養満点のご飯を作り、男子部員には米2合食わせる。 | ||

| ① | 北條英雄(ほうじょうひでお) | ② | カヤック |
| ③ | ④ | 法学部 | |
| ⑤ | 奈良県・西大和学園 | ⑥ | ヒカリ・レーザー |
| ⑦ | 二枚目。いわゆる”イケメン”。きざなやつかと思うも飾らない 気さくな人間で下○タも大好物。レーザーで上回生に挑んで ゆく。 | ||

| ① | 南千晴(みなみちはる) | ② | カヤック |
| ③ | ④ | 経済学部 | |
| ⑤ | 富山県・高岡高校 | ⑥ | X-Lancer(DARK HOURSE) |
| ⑦ | 2010年インカレにおいて、女子カヤックシングル3位になった女子カヤック期待の新星。普段はおっとりしているが、練習中の彼女の顔は真剣そのもの。今後の活躍も期待大。 | ||

| ① | 山崎健史(やまさきたけし) | ② | カヤック |
| ③ | トレーナー・YouTube大臣 | ④ | 工学部情報学科 |
| ⑤ | 京都府・洛星高校 | ⑥ | ヒカリ・レーザー |
| ⑦ | 文化系出身にもかかわらずやたら体がごつい。トレーナーとして トレーニングの知識を深めているほか、YOUTUBE大臣として 練習のビデオのアップロードも担う。 | ||

| ① | 横田睦波(よこたむつみ) | ② | カヤック |
| ③ | ④ | 総合人間学部 | |
| ⑤ | 兵庫県・長田高校 | ⑥ | カッター |
| ⑦ | じつに努力家である。負けず嫌いの性格と、そこらの男子より強いパワーを持つ。おっとりとした雰囲気で周りを和ませる。しかしあげるバーベルは伊藤の体重よりも重い。 | ||

| ① | 吉田奈津美(よしだなつみ) | ② | カヤック |
| ③ | ④ | 法学部 | |
| ⑤ | 福岡県・嘉穂高校 | ⑥ | ヒカリ・タイガー |
| ⑦ | 新歓会計に任命されるしっかり者。しっかりすぎるが故に番長と呼ばれることもあるとか…。練習にも真面目で、すでに冬のタイムトライアルで頭角を現した。期待大。 | ||

 先輩、大丈夫っすか? (2011年初漕ぎにて)
先輩、大丈夫っすか? (2011年初漕ぎにて)
編集後記・謝辞・御願い
後藤 洋三(1964年卒・会長)
久しぶりの河奴発行に皆さんの期待が大変大きいものを感じました。原稿をお寄せ頂いた方、有り難うございました。また、それぞれの卒業年次にお願いした名簿の整備も、期待以上に進みました。連絡を取り合って一度集まろうという機運が盛り上がった卒年もあるようです。
河奴の復刊に当たって、電子配本を採用しては、と言ったご意見も頂きましたが、敢えて今回は9年前と同じスタイルしました。皆さんに、今回の河奴を見て今後のスタイルを考えて頂きたいと考えております。
昨年は、部長として現役を指導してこられた青木謙治先生が大学を定年退職されました。現役の活性化や、特に大学の予算による新艇の購入は、青木先生のご尽力によるところであります。改めて御礼申し上げます。また、後任には松岡俊文先生(大学院工学研究科都市環境工学専攻)が就任されました。松岡先生はカヌー部のOBではありませんが、青木先生とはご専門分野が近く、よくご存じの間柄です。OB・OG会としても一層のご協力をしていきたいと思っております。
さて、今回の河奴では会計報告のページを割愛しています。これは今後のOB・OG会の財政計画をご提案する余裕がなかった事が主な理由です。
昨年末で会費残高はおよそ15万円でした。本年早々に皆さんに会費の振り込みをお願いし、既にある程度の金額が積み上がっております。しかし、新勧費用の支援が目先にあり、やや長期的には部員増に伴う艇の不足が想定されます。さらには艇庫の老朽化もあり、大学からの支援だけでは足りないことが明白です。長期計画を議論する必要がありますが、まずは、200名を超えるOB・OGが忘れずに会費を払って頂けば当面の財政問題は解決します。会費は5,000円/年、学生OBや定職に就いておられない方は1,000円/年です。以下の口座にお振り込み下さい。よろしくお願いします。
三井住友銀行 堺支店 普通 4074499 京都大学カヌー部OB会